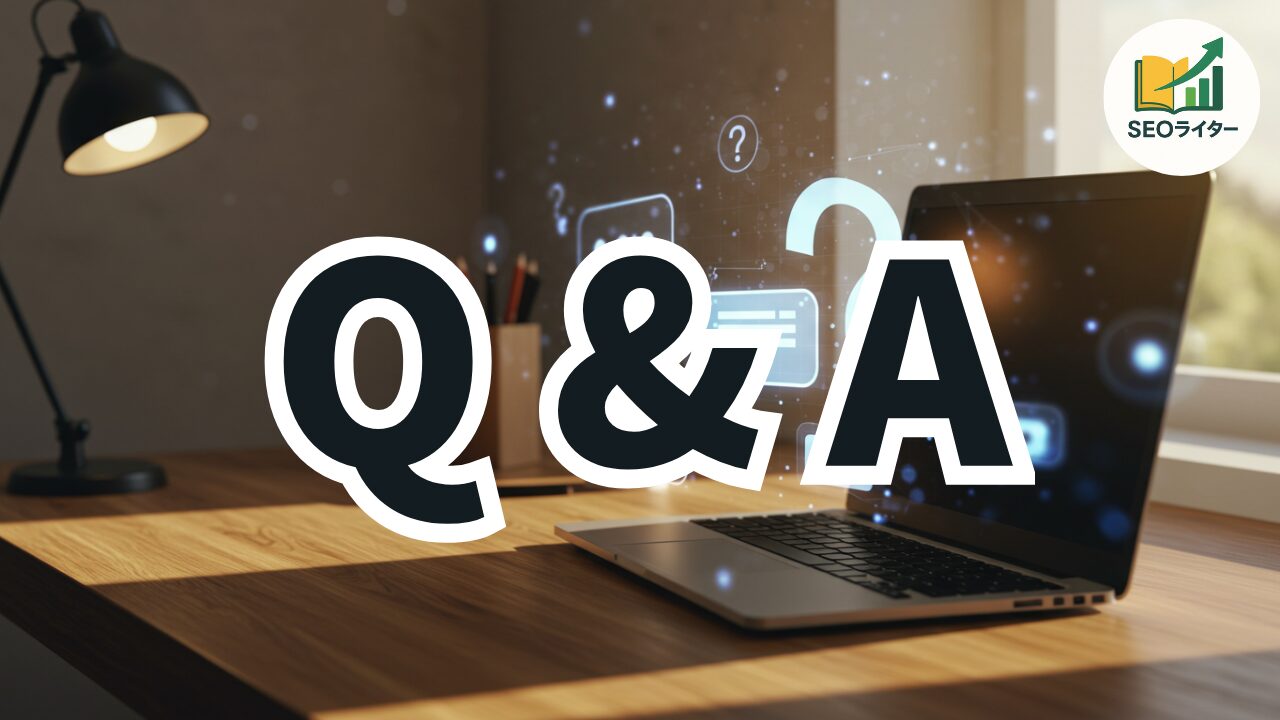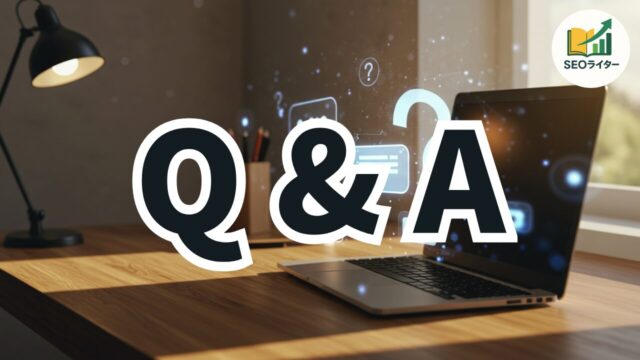AI生成記事を外部のコピペチェックツールで確認したところ、既存のWeb記事と類似度が高いという結果が出てしまった――このような状況に直面すると、どう対処すればよいのか不安になる方も多いでしょう。今回は、万が一生成した記事が既存記事と似てしまった場合の具体的な対処法について解説します。
まず理解しておきたいこと
SEOライターが採用している最新の大規模言語モデルは、毎回異なる表現で文章を生成する特性があるため、完全に同一の文章が生成される確率は極めて低いです。また、詳細なペルソナ設定やコンテンツカスタマイズ機能により、そもそも既存記事と類似したコンテンツを生成させない設計となっています。
しかし、同じテーマや同じキーワードを扱う場合、情報の本質的な内容が部分的に重なる可能性はゼロではありません。特に以下のようなケースでは類似が発生しやすくなります:
- 基本的な情報を扱うテーマ(「〇〇とは」「〇〇のメリット」など)
- 定型的な手順を説明する記事(「〇〇の設定方法」など)
- ペルソナ設定やコンテンツ設定が不十分なまま生成した場合
類似が判明した場合の3つの対処法
コピペチェックツールで類似度が高いと判明した場合、以下の3つのステップで対処してください。
ステップ1: ペルソナ設定を変えて再生成する
最も効果的な方法は、ペルソナ設定を大幅に変更して記事を再生成することです。同じキーワードでも、誰に向けて書くかを変えるだけで、まったく異なる切り口や構成の記事が生成されます。
変更すべきペルソナ要素:
- ターゲット年齢層: 25〜34歳 → 45〜54歳に変更
- 読者の属性: 初心者向け → 中級者・専門家向けに変更
- コンテンツ目的: 情報提供 → 問題解決や商品紹介に変更
- 企業の価値観: 手軽さ重視 → 品質重視に変更
例えば「WordPress プラグイン おすすめ」というテーマでも:
- 初心者向け × 簡単さ重視 → 「初めてでも安心!WordPress必須プラグイン5選」
- Web担当者向け × セキュリティ重視 → 「企業サイトのセキュリティを強化するWordPressプラグイン徹底比較」
このように視点が変われば、記事の内容は大きく変わります。
ステップ2: コンテンツ設定でオリジナリティを強化する
再生成してもまだ類似度が気になる場合は、コンテンツ設定を調整してさらなる差別化を図ります。
調整すべき設定項目:
- 文体スタイルの変更: 解説調 → 会話調、ストーリー調に変更
- よく使う表現を追加: ブランド固有のキーワードや言い回しを登録
- 避けるべき表現を指定: 類似記事で多用されている一般的なフレーズを除外
- 構成のヒントを追加: 独自の展開順序や切り口を明示的に指示
これらの設定により、同じ情報を扱っていても表現方法が大きく変わり、オリジナリティが生まれます。
ステップ3: 独自の情報や視点を手動で加筆する
再生成した記事に対して、あなた自身の経験や知見を追加することで、完全なオリジナルコンテンツに仕上げます。
追加すべき独自要素:
- 自社での実践事例や失敗談
- 独自に収集したデータや統計
- 業界の専門家としての見解
- 最新のトレンドや変化についての考察
- 読者への具体的なアドバイス
この加筆作業により、Googleが重視するE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)も同時に向上します。AI生成記事はあくまで「下書き」と考え、最終的には人間の視点で価値を追加することが重要です。
部分的な類似の場合の対応
記事全体ではなく、特定の段落やフレーズだけが類似している場合は、以下の方法で対処できます:
該当部分の表現を変える
- 言い回しを変更: 「重要です」→「欠かせません」「不可欠です」
- 文章構造を変更: 箇条書き → 段落形式、または逆のパターン
- 順序を変更: 説明する順番を入れ替える
- 具体例を差し替える: 別の事例や数値を使用する
情報の粒度を変える
- より詳細に掘り下げる(深掘り型)
- より広い視点で概要をまとめる(俯瞰型)
- 実践的なHow-toを強化する(実用型)
外部コピペチェックツールの活用タイミング
SEOライターには自動コピペチェック機能は搭載されていませんが、以下のタイミングで外部ツールによる確認を推奨します:
必ずチェックすべきケース:
- 企業サイトやオウンドメディアでの公開前
- クライアントへの納品前
- 収益化メディアでの公開前
- 10記事以上の大量公開前
- 同じテーマで複数記事を生成した場合
確認の目安:
- 類似度30%未満 → 問題なし、そのまま公開可能
- 類似度30〜50% → 一部修正を推奨
- 類似度50%以上 → ペルソナを変えて再生成を推奨
それでも類似が解消しない場合
上記の対処法を試しても類似度が下がらない場合は、そのテーマ自体が非常に一般的で差別化が難しい可能性があります。その場合は:
- テーマ自体を変更する: より具体的なニッチテーマに切り替える
- 複数の視点を組み合わせる: 関連する複数のテーマを統合した記事にする
- 一次情報を大幅に追加: 独自取材やインタビュー内容を中心にする
まとめ
万が一生成した記事が既存記事と似てしまった場合も、ペルソナ設定の変更、コンテンツ設定の調整、独自情報の加筆という3つのステップで対処できます。SEOライターの充実したカスタマイズ機能を活用すれば、同じテーマでもまったく異なる切り口の記事を生成できるため、類似問題は十分に解決可能です。外部コピペチェックツールでの最終確認を習慣化し、必要に応じて上記の対処法を実施することで、完全にオリジナルなコンテンツとして安心して公開できます。
関連記事
- 重複コンテンツ(Duplicate Content)のリスクは?
- AIで生成した記事に著作権侵害のリスクはありますか?
- 生成される記事の文字数や構成のカスタマイズは可能?
- 同じキーワードで複数回生成すると、似た記事になりませんか?
- 効果的な記事生成のコツは?
- 既存記事のリライト・改善機能は?
- AI記事でSEO効果を高めるポイントは?
参考情報・ソース
本記事の内容は、以下の信頼できる情報源に基づいています:
著作権関連
AIツール利用規約・ポリシー
AI生成コンテンツとSEO
E-E-A-T(品質評価ガイドライン)
免責事項: 本記事の情報は2025年10月時点のものです。AI技術やGoogleのアルゴリズムは常に進化しているため、最新の情報は各公式サイトでご確認ください。専門的な判断が必要な場合は、必ず資格を持つ専門家にご相談ください。